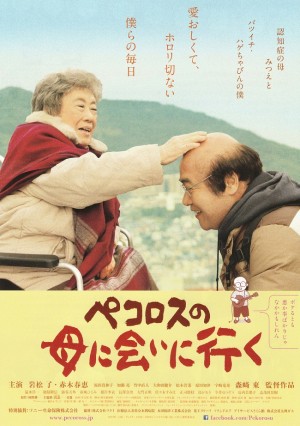最近、おもうこと
50歳から始めた”さをり織” 「自分自身を織り上げる」という創始者・城みさをさんのことばに惹かれました。
定年後の第二の人生、2016年7月に「姉妹塾 SAORIKO-UKO」 を和光市で開所しました。
大好きな”さをり織”を、多くの人に伝えて一緒に楽しみたいと思っています。
もうひとつのチャレンジは、10年間続けているネパールの貧しい家庭の子ども達の就学支援、この活動をもっと広げるために、
2017年4月に「ネパール子ども基金・里親の会」のブログを立上げたことです。
里子が自分自身の将来を切り開くために、私たちのボランティア活動が少しでもお手伝いができればと考えています。
そしてこの「SAORIKO日記」を再開しました。
2017-10-16
2016-06-19
2016-01-16
コカリナ・コンサート
池袋の東京芸術劇場で開かれたコカリナ・コンサートに行きました。
演奏中に写真を写せないので演奏終了後の写真のため、どんな楽器かわかりずらいですが、子ども達が首からぶら下げている小さな木の笛がコカリナです。
コカリナは東欧の民族楽器だったそうですが、黒坂黒太郎氏が日本に紹介し、日本の木工家によって改良されて、精度の高い現在のコカリナが誕生しました。
はじめてコンサートを聴いたのですが、そのやさしい音色に魅了されました。
下の写真のピアノの横には国立競技場の廃材で作った太鼓も写っていますが、コカリナも廃材で作るのです。
会場の2階席には美智子妃殿下が来場されているというアナウンスがあり、ミーハーな私はバックを写したのですが??
2014-06-28
「 いのちと平和と子どもたち 」 川口ぞうれっしゃ2014
埼玉会館大ホールは満杯の観客。第1部は「 TICOBOのガラクタ音楽会 」。
奇妙な出で立ちとガラクタが奏でる音楽に子ども達は魅了されます。
第2部はいよいよ川口ぞう列車合唱団の「ぞうれっしゃがやってきた」
このお話は昭和の始めころから、第2次世界大戦を挟んだ1949年までの間に本当にあった出来事です。
サーカスから名古屋の東山動物園にやってきた4頭の象はたちまち人気者になりました。
でも戦争がはじまり、動物園では悲しいことが次々に起こります。
やっと戦争が終わりましたが、東京の上野動物園には動物が全然いなくなっていました。
東京の子ども議会の代表は沢山の署名を持って、「象を貸してください!」と名古屋の東山動物園の園長さんにお願いに行きます。
そして、象を乗せた列車が東京へ走り出します。
合唱団の子ども達は子どものパートを受け持ち、大きな声で元気に歌います。
お母さんたちの中には小さな幼子を抱きながら歌っている凄いママには驚きました。
元職場の上司の義理妹さんにあたる川口ぞうれっしゃ合唱団の代表・荒木紀理子さんからお手紙をいただき、この日、息子達や孫、地域の友人たち10人で浦和まで出向きました。
新聞に案内された効果で、券は完売の盛況でした。

奇妙な出で立ちとガラクタが奏でる音楽に子ども達は魅了されます。
第2部はいよいよ川口ぞう列車合唱団の「ぞうれっしゃがやってきた」
このお話は昭和の始めころから、第2次世界大戦を挟んだ1949年までの間に本当にあった出来事です。
サーカスから名古屋の東山動物園にやってきた4頭の象はたちまち人気者になりました。
でも戦争がはじまり、動物園では悲しいことが次々に起こります。
やっと戦争が終わりましたが、東京の上野動物園には動物が全然いなくなっていました。
東京の子ども議会の代表は沢山の署名を持って、「象を貸してください!」と名古屋の東山動物園の園長さんにお願いに行きます。
そして、象を乗せた列車が東京へ走り出します。
合唱団の子ども達は子どものパートを受け持ち、大きな声で元気に歌います。
お母さんたちの中には小さな幼子を抱きながら歌っている凄いママには驚きました。
元職場の上司の義理妹さんにあたる川口ぞうれっしゃ合唱団の代表・荒木紀理子さんからお手紙をいただき、この日、息子達や孫、地域の友人たち10人で浦和まで出向きました。
新聞に案内された効果で、券は完売の盛況でした。

2014-06-17
茨木のり子展 世田谷文学館
あやや宅でのお泊り会、夜遅くまで飲み明かした翌朝、世田谷文学館の茨木のり子展へ。少々きつい。
自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ
中学校国語の教科書にも掲載されている「 わたしが一番きれいだったとき 」
朝日新聞・天声人語で紹介された「 倚りかからず 」
そして、「 自分の感受性くらい 」
ポエムの朗読の題材にされてきた詩ばかり。
最愛の夫を亡くして、50歳で韓国語を学び、14年後には韓国現代詩の翻訳刊行を果たしたというあっぱれを知った。
もはや
できあいの思想には倚りかかりたくない
もはや
できあいの宗教には倚りかかりたくない
もはや
できあいの学問には倚りかかりたくない
もはや
いかなる権威にも倚りかかりたくはない
ながく生きて
心底学んだのはそれくらい
じぶんの耳目
じぶんの二本の足のみで立っていて
なに不都合のことやある
倚りかかるとすれば
それは
椅子の背もたれだけ
2014-04-26
人のあかし2014 京浜協同劇団
マリドラさんに声をかけられて、京浜協同劇団創立55周年記念「人のあかし2014」~ある憲兵の記録から~ をいつもの4人組で観劇しました。
聞き慣れない劇団の公演は、チラシのイメージ通り重たい内容でした。
撫順戦犯管理署を舞台に、戦犯の憲兵・土屋芳雄さんをモデルにした芝居です。
「敵をも人間として愛する」ことを徹底した撫順戦犯管理署の教育により、殺しつくし焼き尽くし奪い尽くす残虐な行為を行った侵略軍隊の憲兵が、鬼から人間となり中国人に対して素直に謝罪することが出来た「撫順の奇跡」。
モデルの土屋さんの話を聞き書きした元朝日新聞山形支局員・奥山郁郎さんの『ある憲兵の記録』を元に、和田庸子さんがおじいちゃんが孫に語る様な芝居をめざしてシナリオを書きました。
神奈川芸術劇場の小じんまりした舞台で、大した舞台装置もなく、入れ替わり立ち替わり登場する証言者。
そのスッキリした演出が冴えていました。
土屋さんは2001年に亡くなるまで、「自分は戦争の加害者であり、中国では人間ではなく鬼だった。再びあのような侵略戦争を繰り返してはならない。」と語り続けたそうです。
花鳥賊康繁さんが土屋さんを取材して書いた『人間の良心』を購入しました。
NHKテレビBSプレミアム「新日本風土記」
5月23日(金)PM9:00~10:00
川崎特集で京浜協同劇団と「人のあかし」を取り上げる予定です。
聞き慣れない劇団の公演は、チラシのイメージ通り重たい内容でした。
撫順戦犯管理署を舞台に、戦犯の憲兵・土屋芳雄さんをモデルにした芝居です。
「敵をも人間として愛する」ことを徹底した撫順戦犯管理署の教育により、殺しつくし焼き尽くし奪い尽くす残虐な行為を行った侵略軍隊の憲兵が、鬼から人間となり中国人に対して素直に謝罪することが出来た「撫順の奇跡」。
モデルの土屋さんの話を聞き書きした元朝日新聞山形支局員・奥山郁郎さんの『ある憲兵の記録』を元に、和田庸子さんがおじいちゃんが孫に語る様な芝居をめざしてシナリオを書きました。
神奈川芸術劇場の小じんまりした舞台で、大した舞台装置もなく、入れ替わり立ち替わり登場する証言者。
そのスッキリした演出が冴えていました。
土屋さんは2001年に亡くなるまで、「自分は戦争の加害者であり、中国では人間ではなく鬼だった。再びあのような侵略戦争を繰り返してはならない。」と語り続けたそうです。
花鳥賊康繁さんが土屋さんを取材して書いた『人間の良心』を購入しました。
NHKテレビBSプレミアム「新日本風土記」
5月23日(金)PM9:00~10:00
川崎特集で京浜協同劇団と「人のあかし」を取り上げる予定です。
2014-04-25
2014-04-18
高円寺アフター・アワーズ 冴理さんJAZZライブ 4/18
ワインサロン憲法を開催中のcafe garage Dog berry に突如飛び込んできたNさんに浚われてあややとアフター・アワーズへやってました。
そこは冴理さんのオン・ステージ(2部)でした。
Nさんには以前、映画「カンタ・ティモール」に誘われ、東ティモールという小さな島国を知りましたが、今回のJAZZライブでも何も知らずに来た私たちは満足できるひと時をもらいました。
冴理さんのハスキーボイスがまたジャズ音楽に合い、その世界に引き込まれました。
南浦和でダンスを教えているという友達が飛び入りして踊りを披露。
そしてNさんも参加した東北支援、昨年の8/23~25「きらきらうた旅」のDVDも思いがけずプレゼントされました。
そこは冴理さんのオン・ステージ(2部)でした。
Nさんには以前、映画「カンタ・ティモール」に誘われ、東ティモールという小さな島国を知りましたが、今回のJAZZライブでも何も知らずに来た私たちは満足できるひと時をもらいました。
冴理さんのハスキーボイスがまたジャズ音楽に合い、その世界に引き込まれました。
南浦和でダンスを教えているという友達が飛び入りして踊りを披露。
そしてNさんも参加した東北支援、昨年の8/23~25「きらきらうた旅」のDVDも思いがけずプレゼントされました。
2014-04-13
「 語り奏でる詩 」 井上よしこ
千葉文化センターで開かれた井上よしこさんのピアノと朗読のつどい「語り奏でる詩」vol.2にちゃま2、あややとはるばる出掛けました。
10年以上昔、私のブログを見てポエムの活動に興味を持たれてメールをくださったのが始まり。
なにしろ活動の本拠地が千葉のため、今まで2度ほど参加したのみ。
今回は金子みすゞや中原中也、荻原朔太郎などのよく知った詩が読まれるのと、飛び入りの素人の朗読に井上さんがピアノで即興BGMを付けると言うので興味を持ちました。
朗読は福田素子さん、声優を経てフリーの司会者・ナレーターとして活動中。
井上さんは3才からピアノをはじめ、音楽工房「妙」で音楽と異分野の表現芸術とのコラボを展開中。
久しぶりに会う井上さんとの対面を楽しみにしていたが、残念ながらお話をすることが出来ませんでした。
2014-03-15
映画 カンタ・ティモール
さをり作家・森明子さんの展示会会場のある清澄白河駅下車、寺町通りを抜けた深田荘。
ティモールのお菓子とコーヒー付き1500円なり。
映画は広田奈津子監督が23歳の時のドキュメンタリー作品。
上映後、報道写真記者・南島風渉(はえじまわたる)さんのトークイベントがありました。
最近、どんな集いに行っても高齢者ばかりで世代継承が出来ていないと嘆くことしきりなのですが、今回の映画会は若者であふれていました。
東ティモール民主共和国、名前しか知らない国。
バリ島から1時間余のこの小さな島の東半分だけが、インドネシアから独立したという。
 人類はひとつの兄弟なのさ
人類はひとつの兄弟なのさ父もひとり、母もひとり
大地の子ども
憎んじゃだめさ、叩いちゃだめ
戦争は過ちだ、大地が怒るよ
2013-06-30
昔むかし あったとさ
朗読サークルポエムの指導者・大原穣子先生の出演する「ドラマの方言を考える会」公演日です。
さをり教室からタクシーを飛ばして新宿の「青年劇場」スタジオに飛び込んだのですが、すでに最初の演目が終了していました。
「指導者養成講座」の2日目が終わり、後片付けと明日の「クリエーター会議」の準備でてんやわんやの教室を出たのが開演時間の6時半。
ポエムの他のメンバーは昼の部で観劇しているので、夜の部は私ただ一人でした。
今回の企画・構成を担当した富田祐一さんの朗読の最中にスタジオに滑り込みです。
ふるさとの言葉で語る ~第八弾~
北から南から 訛り言葉の楽しさ プログラム
「ほら吹き比べ」 津軽弁 小川ひかる
「狸の恩返し」 奥州弁 富田祐一
「峠の地蔵様」 村山弁 芝田陽子
「飯盛山と弁天様」 会津弁 河原田ヤスケ
「屋根にのぼった赤牛」 演習弁 外海多伽子
「初午(今昔物語より)」 京ことば 小林由利
「貧乏神と福の神」 博多弁 隈本吉成
「コッペパン」 東京弁 夏巳 涵
「俺ぁ孫のお陰で助かったのだよ」 群読
「3.11 その時」 大原穣子
さをり教室からタクシーを飛ばして新宿の「青年劇場」スタジオに飛び込んだのですが、すでに最初の演目が終了していました。
「指導者養成講座」の2日目が終わり、後片付けと明日の「クリエーター会議」の準備でてんやわんやの教室を出たのが開演時間の6時半。
ポエムの他のメンバーは昼の部で観劇しているので、夜の部は私ただ一人でした。
今回の企画・構成を担当した富田祐一さんの朗読の最中にスタジオに滑り込みです。
ふるさとの言葉で語る ~第八弾~
北から南から 訛り言葉の楽しさ プログラム
「ほら吹き比べ」 津軽弁 小川ひかる
「狸の恩返し」 奥州弁 富田祐一
「峠の地蔵様」 村山弁 芝田陽子
「飯盛山と弁天様」 会津弁 河原田ヤスケ
「屋根にのぼった赤牛」 演習弁 外海多伽子
「初午(今昔物語より)」 京ことば 小林由利
「貧乏神と福の神」 博多弁 隈本吉成
「コッペパン」 東京弁 夏巳 涵
「俺ぁ孫のお陰で助かったのだよ」 群読
「3.11 その時」 大原穣子
2013-06-03
うかうか三十、ちょろちょろ四十
 |
こまつ座誕生29年目の今年、井上ひさし24歳の時の作品「うかうか三十、ちょろちょろ四十」が上演されました。
昨年、「井上ひさし生誕77フェスティバル2012」で、彼の作品を堪能しましたが、これは幻のデビュー作品だそうです。
四谷の出版社の倉庫番をしながら、脚本の懸賞募集に応募し続け、文部省芸術祭脚本奨励賞を獲得したのがこの作品でした。
いつもの長丁場の井上作品とは違い、笑っているうちに幕、会場を出て時計を見ると1時間半弱という短い作品でした。
プログラムで執筆当時の写真を見ると、若い!
演出は井上作品ではおなじみの鵜山仁。
舞台は同じ場面で、プロローグ、9年後の出来ごと、そのまた9年後のエピローグと3場設定。
いつものお国ことばとブラックユーモアに、若くともまさに井上ひさしの感がありました。
2013-03-29
サロン・ド・ポエム
朗読サークル・ポエムの活動は在職中から20年近くなりますが、定年退職後は「サロンド・ポエム」として、方言指導者・大原穣子先生と高岡岑郷先生をお招きしてマリドラ宅でお茶をしながら和気あいあいと練習をしています。
このたび高岡先生がとある教会での発表の場をセッティングしてくださいました。
5月11日の舞台の台本「人が人として生きるために!」が本日出来上がりました。
私たちが読む詩は柴田トヨさんの2冊の詩集の中から選びました。私の読む詩は以下の詩です。
このたび高岡先生がとある教会での発表の場をセッティングしてくださいました。
5月11日の舞台の台本「人が人として生きるために!」が本日出来上がりました。
私たちが読む詩は柴田トヨさんの2冊の詩集の中から選びました。私の読む詩は以下の詩です。
 |
 |
<教わる>
母に縫物を
教わりました
連れあいには辛抱を
教わりました
倅は詩を書くことを
教えてくれました
みんな 私には
役立ちました
そして今
人生の終わりに
人間のやさしさを
震災で教わったのです
生きていて よかった
ポエムを早退して、元職場のホームページプロジェクトの送別会に出かけました。
明治神宮の花見は5時半閉園で観られませんでしたが、懐かしい「ふうが屋」でたんと食べました。
相変わらずの満員ですが、この日は団体客が2組入っていて、我らは異端者の風情。
ポエムを早退して、元職場のホームページプロジェクトの送別会に出かけました。
明治神宮の花見は5時半閉園で観られませんでしたが、懐かしい「ふうが屋」でたんと食べました。
相変わらずの満員ですが、この日は団体客が2組入っていて、我らは異端者の風情。
主賓は定年を1年前にしての異動で少々戸惑っているようでしたが、双子のお嬢さんがこの春めでたく進学したのを手放しで喜んでいました。
お父さん、これから学費がかかりますね、頑張って!!
お父さん、これから学費がかかりますね、頑張って!!
2013-03-15
三月花形歌舞伎
2013-02-08
映画 レ・ミゼラブル
 |
三択で、「東京家族」「最強の二人」「レ・ミゼラブル」
と悩んだのですが、おしゃべりの時間を削っても「レ・ミゼラブル」を観ようという結論に達しました。間違いのない選択だったと思います。
舞台は以前観たことがありますが、舞台の臨調感と映画の持つスケールの大きさを合体したというのでしょうか。
歌を先にレコーディングするのではなく、俳優が実際に演技し、カメラの前で歌っているのをそのまま撮影したという映画に唖然!
最初のシーンからこの映画のスケール大きさが目の中に飛び込んできました。
「下を向いて、下を向いて」とお腹に響く呪うような囚人たちの歌声!
追って!追って!やっと追い詰めたジャンバルジャンに助けられ、自ら死を選ぶジャベール。
吸い込まれるような水面の投身シーン。
クライマックスの蜂起し死んでいった若者たちが蘇る圧巻のシーン。
アカデミー賞8部門ノミネートはいかなる結果に!
2012-12-23
組曲虐殺 井上ひさし生誕77フェスティバル 第8弾
2012-11-24
浩子の絵
2012-11-18
中国王朝の至宝
私の誕生日のこの日、上野の東京国立博物館で開催中の「中国王朝の至宝」を観てきました。
冷たい風が強く吹く上野公園を横切り、イルミネーションを見ながら平成館に向いました。
いろいろ険悪な状態になっている両国ですが、日中国交正常化40周年を記念して展覧会が開催されています。
日本では縄文時代と言われていた頃、中国では初期王朝の夏・殷の時代から、宋までの歴代王朝の出土品を展示しています。
中国4000年の歴史、当時の日本と比較するとその文化の高さに驚かされます。
誕生日会食はうなぎ料理をご馳走になりました。
お店は黒服と和服のサービス担当者、客筋は日本語の巧みな中国の方と年配の女性、派手なスーツの紳士のカップル?と、「若者が入ることなど出来ない店だな」と息子が思わず漏らしていました。
冷たい風が強く吹く上野公園を横切り、イルミネーションを見ながら平成館に向いました。
いろいろ険悪な状態になっている両国ですが、日中国交正常化40周年を記念して展覧会が開催されています。
日本では縄文時代と言われていた頃、中国では初期王朝の夏・殷の時代から、宋までの歴代王朝の出土品を展示しています。
中国4000年の歴史、当時の日本と比較するとその文化の高さに驚かされます。
誕生日会食はうなぎ料理をご馳走になりました。
お店は黒服と和服のサービス担当者、客筋は日本語の巧みな中国の方と年配の女性、派手なスーツの紳士のカップル?と、「若者が入ることなど出来ない店だな」と息子が思わず漏らしていました。
2012-11-15
日の浦姫物語
 |
| 稲若/魚名・藤原竜也 |
 |
| 日の浦姫・大竹しのぶ |
この初演は1978年、文学座の杉村春子に当て書きした作品。
演出は木村光一だったが、今回の演出は蜷川幸雄。
15歳から老婆までを演じ分け、近親相姦で兄と息子を愛する女を演じる大竹しのぶの演技に脱帽。
2012-08-20
スーちゃんの「黒い雨」
 |
| 「戦争は、体の中で続いています」のポスター |
埼玉会館で上映された「黒い雨」を観てきました。
会場前に飾られた「体の中で、戦争は続いています」というメッセージの入ったスーちゃんのポスターが印象的でした。
8月6日投下の日、瀬戸内を渡る船で黒い雨を浴びた2次被曝、凄惨な広島市内を逃げ歩く、当時の描写が怖い。
被爆者というレッテルによる見合いの破局が戦後の差別を物語っています。
いつもは静かに石象を掘っている男が、エンジンの音を聞くや否や、戦車の猛攻を受けたトラウマによって豹変する姿も戦争の爪痕を強烈に伝えています。
上映と併せて、中原中也賞詩人のアーサー・ビナードの講演会があったのですが、残念ながら聴くことが出来なかったので、孫に絵本を購入しました。
「イッツ・ア・スモールワールド」 ~みんなとなりどうし~ ウオルト・ディズニー生誕110年記念絵本。
絵:ジョーイ・チョウ 日本語詩:アーサー・ビナード
PS
近くのお蕎麦屋さんで昼食を食べ、浦和駅からバスを乗りついて、協同研の I さん宅へ。
iPad用のバックのベルトと中ポケットのお直しをしてもらい、さをりの布のロックミシンも図々しくお願いして帰ってきました。
登録:
投稿 (Atom)