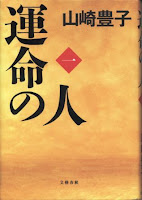エッセイスト藤田市男の、朗読でよびかける「いま死なないでキャンペーン」が、8月24日スタートします。
子どもや保護者の集まりに、「いま死なないで」のメッセージを伝える30分のプログラムです。
小学校、中学校の始業式を皮切りに、藤田市男のミニトークと船尾佳代アナウンサーによる朗読。
交通費のみの無料出張だそうです。
子どもたちへ (藤田市男のエッセイ「たいせつなあなたへ」から一部抜粋)
キミの生まれた日のことは忘れない。
うれしくてうれしくて、なんどもキミのホッペに顔をくっつけていた。
子どもたち。親には心配かけていいんだよ。
どうせ親なんて、どんなときでもキミたちのことを心配するんだもの。
いや、モノワカリのいい親を演じているんじゃなくてね。
もしキミたちが急にイイコになったりしたら「うちの子はいい子すぎるんじゃないかな」って、
きっとまた心配しちゃうんだ。
キミたちが悪いことをしたら、そりゃあ叱る。親だもの、しっかりと叱る。
でも、だからといって、キミたちのことを嫌いになんか、けっしてなれない。
信じておくれ、子どもたち。どんなに心配かけられたって、それはみんな受けとめてみせるから。
そう、たったひとつのこと以外はね。
聞いておくれ、子どもたち。キミたちの死よりも大きな悲しみなんて、私は知らない。
いまさらだけど、もういちど親を信じてくれないかな。
またあのころのように、親を信じてくれないかな。
いつも手をつないでいたあのころのように、抱っこされることが大好きだったあのころのように
また親を信じてくれないかな。
難しいかな。頼りないかな。もう、信じられないかな。
死を選ぶ前に、お願いだから、もういちど話しをしてくれないかな。
その苦しみを預けてくれないかな。
わたしたちもいっしょに苦しませてくれないかな。
お願いだから、子どもたち。きらいなヤツのために死んだりするな。
好きな人のために生きてくれ。
キミのことを大好きだって言う人が、キミのまわりに大勢いることに気づいてくれ。
そしてなにより、キミ自身のために生きてくれ。
キミがいなくなるその悲しみよりも大きなものなんて、わたしたちにはないのだからね。
お願いだから子どもたち。
わるい子になってもいいから、ダメな子になってもいいから、ずっとずっと生きておくれ、
子どもたち。
PS
10:00から協同研の事務所で、無線LANに接続してのインターネット学習会を開催しました。
どうにか運営委員の半数がGmail を取得して、「会員情報発信サイト」の編集権限を得ることが出来ました。
Gmail 取得に時間がかかり、投稿の練習まで行きませんでした。前途多難。